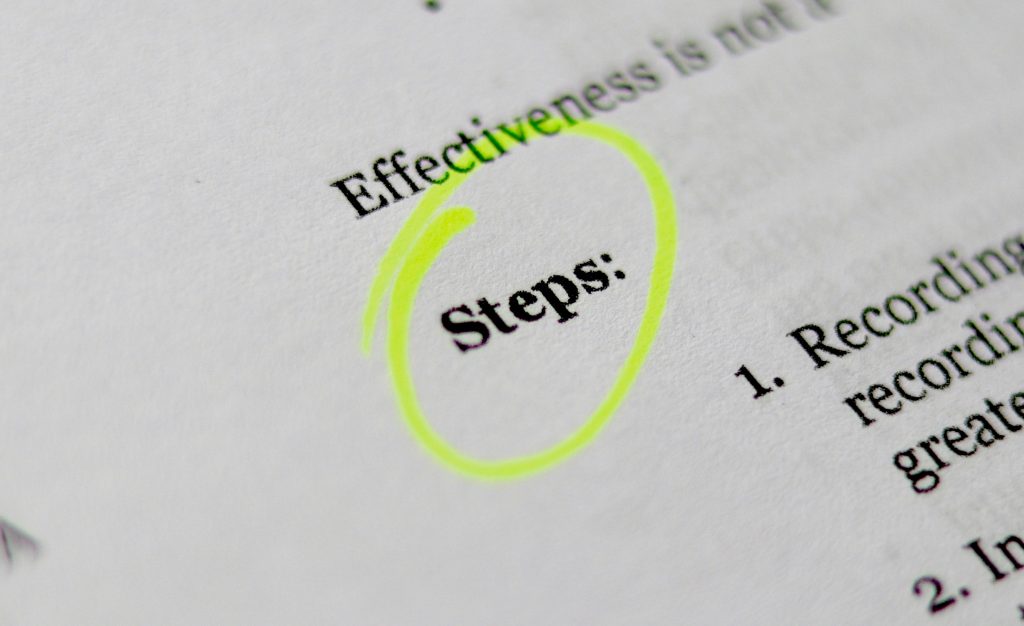
商標登録をするには特許庁に申請する必要があります。この記事では、商標登録のまでの流れについてステップごとに詳しく解説します。
商標登録までの大まかな流れは以下の通りです。
1, 先行商標調査(他社の商標登録の状況を調査する)
2, 出願(出願書類を作成し、特許庁へ出願する)
3, 審査(特許庁の審査を受ける)
4, 登録査定(もし登録できない理由がある場合は拒絶理由通知が送付される)
5, 登録料納付(登録料を納付すると商標権が発生する)
◇目次
【商標登録までの流れ】
商標登録までの流れは、以下の通りです。
1,先行商標調査を行う
自分が考えた商標案が、同一または類似の商品やサービスにおいてすでに登録されていたり、商標出願されていたりしたら、原則としてその商標は使用できず、商標権の取得もできません。
そのため、商標を出願する前に、その商標の使用可否や登録可否を調べる必要があります。出願費用を無駄にしないために、事前の商標調査(先行商標調査)をすることが重要です。
– Cotoboxで先行商標調査をする
Cotoboxは、特許庁と同じデータソースを使用した無料のサービスです。初めて商標検索する人でも使いやすいシンプルな操作画面が特徴です。
先行商標調査では、同一だけでなく類似した商標の調査も重要です。Cotoboxの類似商標検索機能は、高度なAI技術を活用して類似商標を網羅的に調査し、類似度の高い商標を抽出するサービスです。
– J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で先行商標調査をする
J-PlatPatは、経産省所轄の独立行政法人「工業所有権情報・研修館(INPIT)」が無料で提供しているサービスです。日本国内で登録された全ての商標を網羅しているため、情報の信頼性が高く、弁理士も利用しているサービスです。
また、J-PlatPatには、商標の出願情報だけでなく、登録情報も公開されています。なお、J-PlatPatの検索は、類似度が高いものから、それほど高くないものまで含めて、関係する商標すべてを抽出・提示するサービスです。そのため、商標の類否判断自体は、検索者自らが判断する必要があります。
2, 出願書類を作成する
商標登録の出願には、大きく分けて「書類出願」と「インターネット出願」の2種類があります。
それぞれの特徴と手順を解説します。
– 書類出願
出願書類を紙で作成し、郵送や特許庁の窓口に直接提出する方法です。
インターネット出願ではかからない、電子化手数料を追加で支払う必要があります。
< 手順 >
1)特許庁の知的財産・相談支援ポータルサイトから「商標登録願」をダウンロードします。
2)ダウンロードした願書に必要事項を記入します。印字と手書きいずれも可能です。
3)規定の出願料分の特許印紙を購入して指定の箇所に貼り付けます。
4)記入した願書を特許庁に郵送、または、 特許庁の受付窓口に直接持参します。
5)電子化手数料を納付します。電子化手数料の払込用紙は、出願日から数週間後に送付されます。
– インターネット出願
インターネット出願ソフトを使用して、オンラインで出願書類を提出する方法です。
インターネット出願ソフトは、Windowsにのみ対応しており、ソフトの入手にはメールアドレスが必要です。また、出願人の身元を確認するために電子証明書も必要です。
< 手順 >
1)パソコンに、特許庁の電子出願ソフトサポートサイトから「インターネット出願ソフト」をダウンロードします。
2)電子証明書を準備します。出願人が個人か法人かにより、利用できる電子証明書が異なります。
3)インターネット出願ソフト上で、特許庁に申請人利用登録を行います。識別番号の取得していない場合は、このタイミングで識別番号の取得の手続きも合わせて行うことができます。
4)特許庁に提出する願書をHTML形式で作成します。
5)出願料の納付方法を決め、納付方法に応じた設定を行います。※
6)インターネット出願ソフトを通じて、特許庁に願書を提出します。
※ インターネット出願での出願料の納付は、選択した納付方法によって、手続きのタイミングや設定方法が異なります。
インターネット出願の手順についての詳細はこちらもご参照ください。
▶特許庁:初心者のための電子出願ガイド
▶特許庁:電子出願ソフトサポートサイト:操作マニュアル
▶特許庁:電子出願ソフトサポートサイト:ユーザガイド
* 出願時の費用について
出願時に出願料や電子化手数料として特許庁に納付する金額は以下の通りです。
| 出願料 | 3,400円+(8,600円×区分数)(非課税) |
| 電子化手数料 | 2,400円+{ 800円 ×願書のページ数 }(非課税) |
※出願料は、区分数に応じて金額が変わります。
※インターネット出願の場合は、電子化手数料は不要です。
出願料について、詳しくはこちらの記事をお読みください。
▼商標登録の費用と相場
3, 特許庁の審査を受ける
特許庁の審査官による方式審査、実体審査を経て、商標の登録可否が判断されます。
<方式審査>
出願書類が商標法に沿った形式で記載されているかを確認します。書類に不備がある場合、出願人に不備の修正(補正)を指示する「手続補正指令書」が届きます。この修正は、指定期間内に行う必要があります。
<実体審査>
・出願された商標が、他者の商標と同一または類似していないかという点や、一般名称や独占に適さない言葉でないかという識別力の点など、様々な観点から登録を認めてもよい商標であるかを判断します。
・審査官は、1つの区分の中に、類似群コードが23種類以上ある場合、広い範囲の商品・サービスを選んでいると判断し、拒絶理由を通知します。
このふたつの審査を通過すれば、商標登録の手順へと進みます。
4, 審査結果を受け取る-登録査定と拒絶理由通知-
出願された商標が登録可能と判断された場合は「登録査定」が送られてきます。
一方、特許庁の審査で商標登録できない理由(拒絶理由)が見つかった場合、拒絶理由が記載された拒絶理由通知書が送られてきます。これを拒絶理由通知といいます。
出願人は、拒絶理由通知に対して補正書を提出して出願内容の補正を行ったり、意見書の提出により特許庁の審査結果に対して反論をしたりすることができます。
拒絶理由通知書の対応(中間手続)は、多くの案件で発生します。商標権を取得するには、中間手続は避けては通れないものとお考えください。
「拒絶理由通知」に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
▼商標登録の拒絶理由通知について
* 拒絶査定
特許庁の拒絶理由通知の後、中間手続に対応しても、なお特許庁が商標登録要件を満たしていないと決定した場合には、「拒絶査定」が送られてきます。
拒絶査定について不服がある場合、出願人は、審査結果の撤回を求める審判(拒絶査定不服審判)を請求することができます。
拒絶査定不服審判を請求するための審判請求書には、拒絶査定を取り消すべき理由等を記載します。
拒絶査定不服審判は、特許庁の複数の審判官により構成された合議体が審査を行うため、より慎重な審査が期待できます。(拒絶査定不服審判は、特許庁内の不服申立ですが、準司法的手続が採用されています。そのため、拒絶査定不服審判への不服申立は、一審を省略し、知財高裁への出訴となります。)
拒絶査定不服審判の請求は、拒絶査定を受け取った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
5, 登録料の納付
登録査定の受け取り後、商標を権利化する場合は、登録査定を受け取った日から30日以内に登録料を納付します。
登録料を納付すると設定登録され、商標権が発生します。
登録料を支払わないと出願却下処分となり、その後は権利化することができなくなるため、納付期限にはご注意ください。
5年分ずつ前期・後期に分けて納める「分割納付」と、10年分をまとめて納付する「一括納付」の2種類から選択できます。
■ 特許庁に支払う登録料(5年分) 17,200円×区分数(非課税)
■ 特許庁に支払う登録料(10年分) 32,900円×区分数(非課税)
登録料について、詳しくはこちらの記事をお読みください。
▼商標登録の費用と相場
【登録商標の更新】
商標には有効期限(存続期間満了日)があります。商標の有効期限(存続期間満了日)は、特許や意匠と異なり、更新登録申請をすることで更に延長ができます。更新する際は、所定の手続きと、更新登録料の納付が必要です。
更新登録料は、以下の通りです。
■ 10年ごとの一括納付の場合、43,600円×区分数
■ 5年ごとの分割納付の場合、前期・後期とも、22,800円×区分数
詳しくは以下のページで詳しく解説しています。
▼商標の更新にかかる費用
なお、特許庁の「特許(登録)料支払期限通知サービス」を利用することで、更新のお知らせをメールで受け取ることができるようになります。サービスの内容の詳細はこちらをご覧ください。
▼特許庁:特許(登録)料支払期限通知サービスについて
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/kigen_tsuchi_service.html
【出願料・登録料・更新料の納付方法】
手数料の納付方法は以下の通りです。
| 納付方法 | 概要 | 特許(登録)納付書の提出形態 | 特徴 | |
| 書面 | オンライン | |||
| 1. 特許印紙 | 特許(登録)料納付書に特許印紙を貼り付けます。 | ○ | × | 事前手続きがないため、特許(登録)料納付書の提出が迅速に行えます。 |
| 2. 予納 | 特許庁に予納台帳を開設し、そこから必要な金額を引き落とします。 | ○ | ○ | 特許庁に開設した予納台帳に納付する見込み金額を予め預け入れておくことで、いつでも手続きをすることができます。 |
| 3. 現金納付 | 特許庁専用の振込用紙を使って、銀行へ入金します。 | ○ | × | 料金を振り込んだ証明書(納付済証)を特許庁へ提出する必要があります。 |
| 4. 電子現金納付 | Pay-easy対応のネットバンクまたはATMで入金します。 | ○ ※ 事前手続をするために、電子出願ソフトが必要 | ○ | 納付のたびに電子出願ソフト上で納付番号を取得する必要があります。 |
| 5. 口座振替 | 銀行口座から必要な金額を引き落とします。 ※ 自動的に引き落としはされません。 | × | ○ | 銀行口座に必要な金額を預け入れておくことで、いつでも手続きをすることができます。 |
| 6. クレジットカード | 「3Dセキュア」登録済のクレジットカードにて納付を行います。 | ○ ※ 特許庁窓口で手続する場合のみ可能 | ○ | クレジットカードの3Dセキュア登録が必要です。 |
【出願しても商標登録できない場合もある】
特許庁の審査官による実体審査において、以下に該当する場合は、商標登録できないと判断されます。
(1)自己と他人の商品・役務を区別することができないもの(識別力)
(2)公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの
(3)他人の登録商標又は周知・著名商標等と紛らわしいもの
「出願された商標が登録できないもの」に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
▼商標登録の拒絶理由通知について
【商標登録の依頼先別のプロセス】
ここまで読んでみて、「商標出願は大変そう」と感じた方も多いのではないでしょうか。
特許庁での手続きのプロセスは大きく分けて二つあります。
1,出願人が特許庁への手続きを【直接】行うパターン。
2,弁理士が特許庁への手続きを【代理】で行うパターン。出願人が弁理士に手続きを依頼します。
2についてはさらに、弁理士への依頼のプロセスによっても分けられます。
2-1,出願人が自分で弁理士を探す
2-2,オンラインサービスを通じて弁理士を紹介してもらう
これら3つのパターンは、それぞれ手続きの流れや工数が異なります。
工数の違いは以下の表の通りです。どのケースが自分にとって適切かをご検討ください。
| 1,【直接】 出願人が自分で行う ※書類出願の場合 | 2-1,【代理】 出願人が自分で弁理士を探す | 2-2,【代理】 出願人がオンラインサービスを通じて弁理士に依頼 |
|---|---|---|
| ①商標制度について調べる ②出願する商標の検討 ③区分の選定 ④先行商標調査 ⑤出願書類の作成 ⑥郵便局へ事前連絡 ⑦郵便局で出願料の特許印紙を購入 ⑧特許庁へ出願書類を郵送 ⑨払込用紙で電子化手数料を納付 ⑩特許庁審査待ち(数ヶ月) ⑪登録査定(審査OKの通知) ⑫登録料の納付書類を準備 ⑬郵便局へ事前連絡 ⑭郵便局で登録料の特許印紙を購入 ⑮特許庁へ登録料の納付書類を郵送 | ①特許事務所や弁理士を探す ②弁理士との面談を設定 ③弁理士との面談 ④弁理士による先行商標調査1回目 ⑤調査報告書の受取 ⑥出願について検討 ⑦出願の意思を弁理士に連絡 ⑧弁理士による先行商標調査2回目 ⑨出願料を弁理士に支払 ⑩特許庁審査待ち(数ヶ月) ⑪登録査定(審査OKの通知) ⑫登録料を弁理士に支払 ⑬登録証を弁理士から受取 | ①オンラインで無料の簡易先行商標調査 ②出願料を弁理士に支払(申込) ③弁理士に出願内容相談 ④弁理士による先行商標調査 ⑤出願の意思を弁理士に連絡 ⑥特許庁審査待ち(数ヶ月) ⑦登録査定(審査OKの通知) ⑧登録料を弁理士に支払 ⑨登録証を弁理士から受取 |
| 15ステップ | 13ステップ | 9ステップ |
商標登録の依頼先別の費用について解説している記事がありますので、ぜひこちらもご参考にしてください。
▼商標登録の費用と相場
【商標登録の依頼先別のポイント】
それでは最後に、上記を踏まえて、出願人が直接手続きをするパターンと、弁理士に代理を依頼するパターンのそれぞれのポイントを簡単にご説明します。
– 出願人が自分で特許庁に商標出願する
上記の表のように、出願人が商標登録の手続きを自分で行う場合、弁理士に依頼するのに比べて多くの工数を一人でこなすことになります。
自分で行う場合の一番大きな懸念は、特許庁に提出した書類に不備がある可能性が高い点です。適切な書類を作成するには経験が必要であるためです。
まず、指定商品・指定役務という商品・役務についての国際分類に基づき出願内容を決め、出願書類を作成するのですが、これが極めて専門的な内容です。
また、先行商標調査は、CotoboxやJ-PlatPatなどでできるといっても、最終判断はご自身で行なう必要がありこの判断が大変難しいものです。また、最近になって厳しくなってきた識別力は、CotoboxやJ-PlatPatなどのツールでは確認できないため、ご自身で判断する必要があり、これまた大変難しいものです。
さらに、出願するマーク(商標)を何にするか、外国出願の基礎出願として十分かなど、国内外の商標制度について、経験に基づく総合的な判断が求められます。
実際に、商標登録の専門的な知識が不足した中で出願を進め、運よく商標登録になったが、間違った指定商品・指定役務を登録をしてしまったために、保有する意味がない商標登録を登録しただけという事態があります。
そして、商標登録は、事業を保護するために行うものです。単に事務的な手続きをして商標登録ができれば良いというのではなく、事業を有効にサポートできる商標権が取得できて初めて成功と言えます。この観点からは、商標戦略、商標管理の発想も必要になるでしょう。
自分で商標出願をする場合、事業の保護という観点ではリスクがありますので、十分に注意して手続きを進めるとよいでしょう。
全国47都道府県に設置されているINPIT知財総合支援窓口で、商標登録などの知的財産に関するアドバイスや支援を無料で受けることができます。
自分で特許庁に商標出願する場合は、積極的に活用しましょう。
▼INPIT特許庁知財総合支援窓口
https://chizai-portal.inpit.go.jp/about
– 商標登録を弁理士へ依頼する
商標登録の手続きは、専門的な知識が必要であるため、知的財産の専門家である弁理士に依頼するケースが多いです。
商標登録をご検討の初期段階から弁理士に依頼することで、早く確実に、安心して進めることができますので、お早めに弁理士へ相談することをおすすめします。
▼弁理士の商標登録における役割とは?
また、上記の通り、弁理士に依頼する方法は、自分で弁理士を探す方法と、オンラインサービスを利用して弁理士を探す方法の二つの方法があります。
それぞれの方法によって、かかる費用や利用のしやすさなどの違いがありますので、比較してご自身にあった方法を選択するとよいでしょう。
▼商標登録の依頼先別の費用について解説:商標登録の費用と相場
